2025年4月に省エネ基準適合が義務化されました。どのような内容かご存知でしょうか?
また、内容だけではなくその影響についてもしっかりと理解しておかなければなりません。
お客様に関わる部分もあるので、このタイミングでしっかりと理解しておきましょう。
この記事では、省エネ基準適合の義務化について詳しく解説します。
省エネ基準や省エネ住宅の種類についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
- 省エネ基準適合義務化の内容
- 省エネ基準適合が義務化される影響
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
省エネ基準とは?わかりやすく解説

省エネ基準は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律で規定された基準です。
省エネ基準の適合性は、以下の2つで判定されます。
- 外皮性能基準
- 一次エネルギー消費量基準
住宅の場合は両方に適合しなければなりません。
また、省エネ住宅を実現するためのポイントは、以下のとおりです。
- 断熱:住宅内外の熱移動を少なくする
- 日射遮蔽:日射を遮り、気温の上昇を抑える
- 気密:空気の流れを抑えて、室内を一定の温度に保つ
お客様に伝えるときは、それぞれについて簡単な補足ができるとよいでしょう。

省エネ住宅の種類

省エネ住宅は、大きく7種類に分かれています。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 省エネ基準適合住宅 | 建築物省エネ法の規定をクリアした住宅 |
| ZEH住宅 | エネルギー収支がプラスマイナスゼロになる住宅 |
| 長期優良住宅 | 断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上を満たす住宅 |
| LCCM住宅 | CO2収支をマイナスにする住宅 |
| 認定低炭素住宅 | 二酸化炭素の排出を抑える措置をした住宅 |
| 性能向上計画認定住宅 | 省エネ基準をさらに高い水準でクリアしたと行政が認めた住宅 |
| スマートハウス | 省エネ性能とITツールを掛け合わせた住宅 |
省エネ住宅と一括りに呼ばれますが、実際にはさまざまな種類があります。
それぞれの特徴を簡単に説明できるようにしておくとよいでしょう。
省エネ基準適合住宅については、以下の記事でも詳しく解説しています。

省エネ基準適合が義務化される!その内容とは?
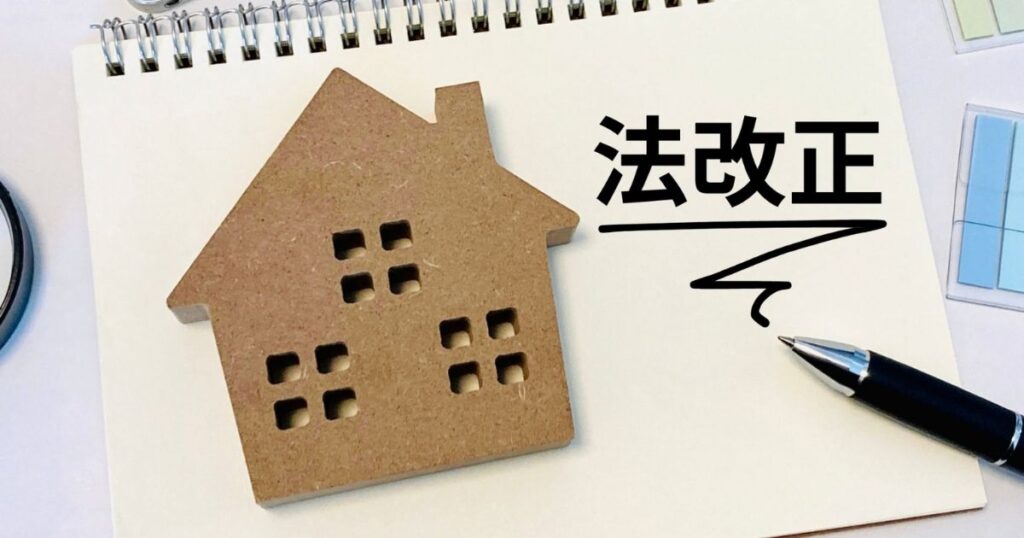
2025年4月の省エネ基準適合義務化の内容は、以下のとおりです。
- 原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられる
- 基準を満たしていなければ建築できなくなる
- 増改築箇所も適合が必要になる
それぞれの詳細を見ていきましょう。
原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられる
このたびの法改正で、原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。
従来は、中規模以上の新築非住宅だけが対象でしたが、2025年4月からはすべての新築住宅、300平方メートルを下回る小規模の非住宅も対象です。
また、増改築するときは、その部分のみ省エネ基準に適合している必要があります。
基準を満たしていなければ建築できなくなる
省エネ基準適合義務化で、省エネ基準を満たしていなければ建築できなくなりました。
建築確認の手続き中に省エネ基準への適合が審査されますが、以下のケースでは確認済証が発行されないので、建築の着工や建物の使用開始が遅れます。
- 省エネ基準をクリアしていない
- 必要な手続きをしていない
建築士などは、省エネ性能向上について建築主に説明する必要があります。
増改築箇所も適合が必要になる
先ほども少し触れましたが、省エネ基準適合義務化により増改築箇所も適合が必要になります。
増改築した際、もともとは既存箇所を含めた建築物全体で、省エネ基準の適合性が判定されていました。
しかし、今回の義務化により、増改築箇所のみで省エネ基準の適合性が判定されることになりました。
混同しないように注意しましょう。
省エネ基準適合が義務化されることによる影響

省エネ基準適合が義務化されることによる主な影響は、以下のとおりです。
- 建築費用が増加する可能性がある
- 工程に変更がある可能性がある
- 築古物件の改修の需要が高まる可能性がある
どのような影響があるのか理解しておくことは非常に重要です。
一つずつ見ていきましょう。
建築費用が増加する可能性がある
省エネ基準適合が義務化されたことで、建築費用が増加する可能性があります。
これは、省エネ基準をクリアするために、新しい建材、設備を導入しなければならないからです。
また、分譲住宅は今までも省エネ基準を満たす住宅が多くありましたが、注文住宅にはやや影響があると考えられています。
さらに、省エネ基準を重視していなかった業者は、建築費用について大きく見直さなければならないかもしれません。
工程に変更がある可能性がある
省エネ基準適合が義務化されたことで、工程に変更がある可能性があります。
省エネ基準に適合するためには、設計段階から断熱性能、設備性能に配慮しなければなりません。
さらに、新基準への対応、知識の習得、手続きのフローの確認なども必要です。
そのため、一部の工程だけではなく、全体にまで影響が出る可能性があります。
築古物件の改修の需要が高まる可能性がある
省エネ基準適合義務化により、築古物件の改修の需要が高まる可能性があります。
たとえば、2000年より前に建てられた住宅は現在の省エネ基準に適合していません。
そのため、改修を希望する人が増えることが予想されます。
また、2000年代に建てられた住宅であっても、省エネ性能の引き上げを目指した需要が生じることも考えられます。
省エネ基準適合義務化以降に住宅を買うならZEH水準以上がおすすめ

今後お客様が住宅購入を検討しているなら、ZEH水準以上がおすすめです。
理由は大きく2つあります。
- 2030年にはZEH水準が住宅のスタンダードになる可能性がある
- 光熱費を削減できる
詳しく見ていきましょう。
2030年にはZEH水準が住宅のスタンダードになる可能性がある
2030年にはZEH水準が住宅のスタンダードになる可能性があります。
国土交通省の計画で、2030年までにZEH水準への引き上げが検討されています。
そのため、現在は基準をクリアしていても、基準が引き上げられたことによりたった数年で基準を下回ってしまう恐れがあることは知っておかなければなりません。
最初からZEH水準以上の住宅を購入すれば、たった数年で基準を下回ったと後悔することもないでしょう。
光熱費を削減できる
ZEH水準をクリアするような住宅は、断熱性能が高く、エネルギー消費効率が良いのが特徴です。
そのため、夏は涼しく、冬は暖かい部屋を実現でき、エアコンの使用を抑えられます。
結果、光熱費を削減可能です。
電気料金の高騰が続いている昨今、省エネ性能が高い住宅は魅力的でしょう。
構造計算のことならMake Houseにご相談ください

省エネ基準適合義務化により、原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。
その結果、建築費用が増加する可能性があったり、工程が変更する恐れがあったりと、お客様にも影響が出るケースがあります。
省エネ基準適合の義務化による影響について、誰かに説明できるくらい理解を深めておくとよいでしょう。
省エネ住宅についてどう対応すべきか悩んでいる場合は、以下の資料をダウンロードしてみてください。
「GX志向型住宅」に工務店はどう対応すべきか?わかる資料
\これを読めばどう対応すべきかわかります/

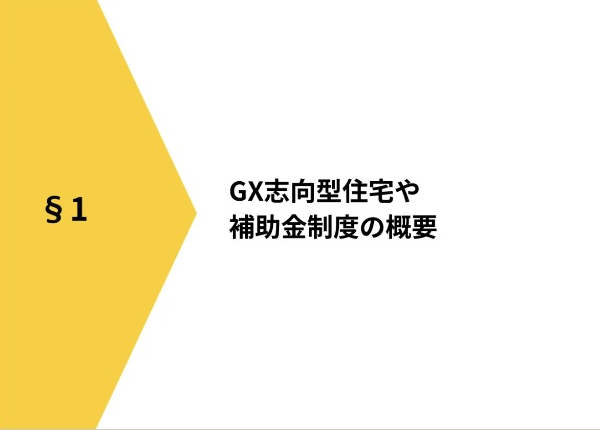
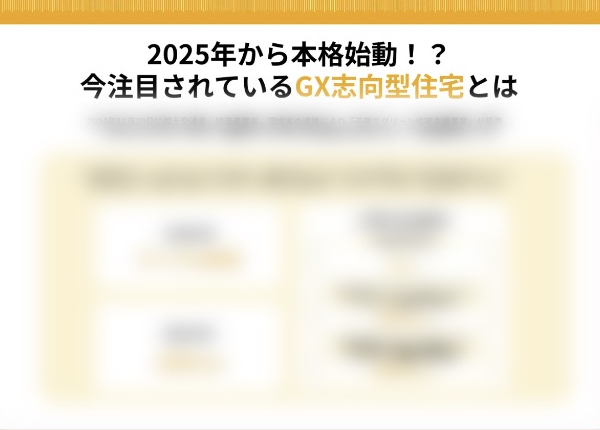
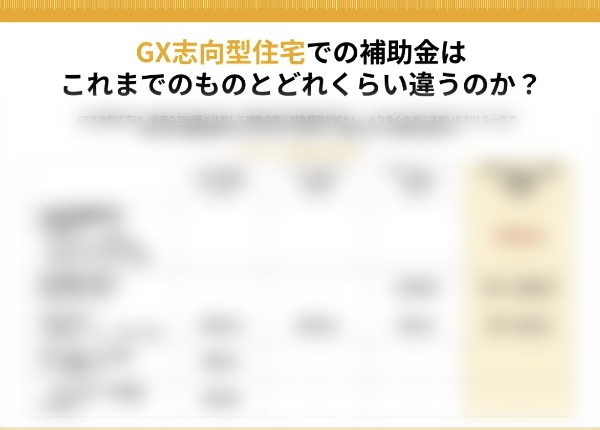
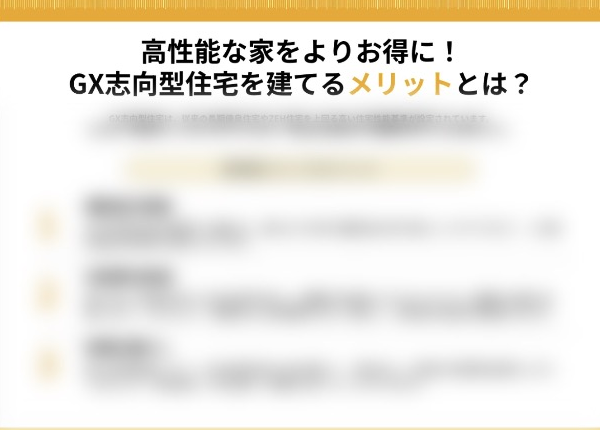
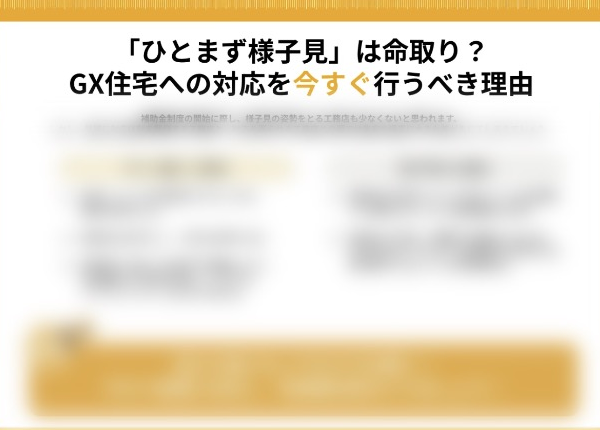
.png)
