建築基準法の改正で耐震基準がどう変わったかは把握できていますか?
日本は地震大国です。耐震については多くのお客様が気にするポイントであり、把握しておいて損はありません。
実際にどの程度の地震に耐えられるのかまで説明できれば、お客様からの信頼もより確かなものとなるでしょう。
細かいことかもしれませんが、ここで頭に入れておくのがおすすめです。
この記事では、建築基準法の改正で耐震基準がどう変わってきたのかをわかりやすく解説します。
「耐震基準についての知識が曖昧である」「どのように変わってきたのかわからない」という人は、ぜひ最後までご覧ください。
- 建築基準法の改正で耐震基準がどう変わってきたか
- 実際どのくらいの地震なら耐えられるのか
- 耐震基準を確認する方法
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
耐震基準は建築基準法により定められている
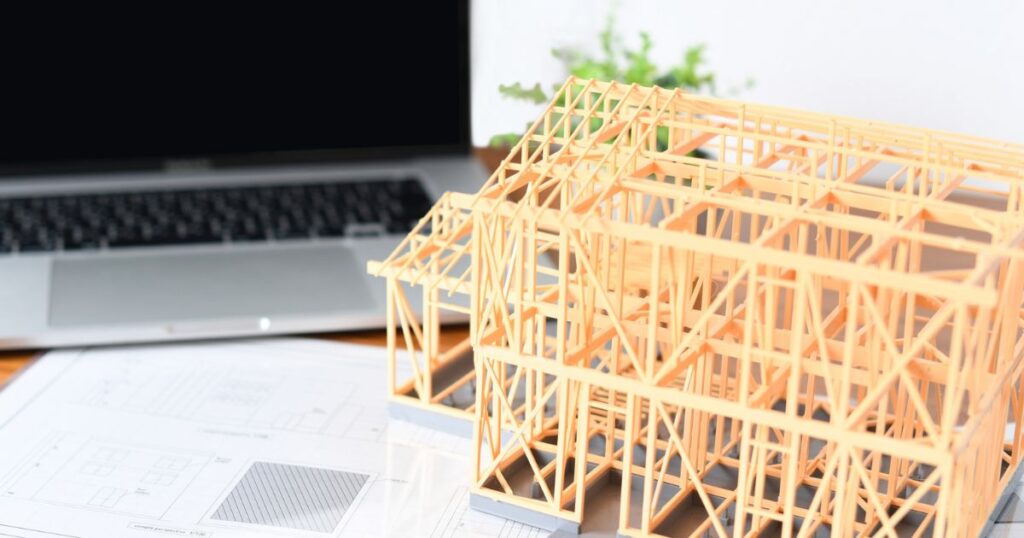
耐震基準は、地震に対して建物が安全であるかどうかを判断するための基準です。
建築基準法が定めているルールであり、住宅を建築する際は最新の基準を遵守しなければなりません。
また、耐震基準と似た言葉に「耐震等級」があります。
耐震等級は住宅性能表示制度に基づく耐震性の判断基準のことで、等級が1〜3に分かれています。
ただし、耐震等級は任意の制度であり、取得することは義務ではありません。
耐震基準と混同しないように注意しましょう。
建築基準法の改正で耐震基準は見直されている

建築基準法の改正で耐震基準は見直されています。
以下の3つの基準について詳しく見ていきましょう。
旧耐震基準|1971年
旧耐震基準は、1968年に起きた十勝沖地震の教訓を踏まえて1971年に改正されました。
とくに、鉄筋コンクリート造の建物のせん断補強基準が強化されたのが特徴です。
さらに、柱の強度についての基準も見直しが図られ、これまでよりも大きな地震に耐えられる構造が求められるようになりました。
この時点では、安全性が大きく改善されることが期待されていました。
新耐震基準|1981年
新耐震基準は、1978年に起きた宮城県沖地震をきっかけに改正されました。
新耐震基準では、以下の2つの概念が導入されています。
- 許容応力度計算
- 保有水平耐力計算
新しい概念が導入されたことで、耐震設計の精度が大きく向上しています。
より安全な建築物の実現を目指したのが新耐震基準だと覚えておきましょう。
なお、新耐震基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

現行の耐震基準|2000年
現行の耐震基準は、1995年に起きた阪神淡路大震災を契機として設定されました。
現行の耐震基準では、とくに木造住宅について見直しが図られており、木造住宅だったとしても事実上地盤調査が必須となりました。
また、柱、筋交いを固定する接合部についても金物が指定されており、さらには耐力壁の配置のバランスに関しても基準が明確になっています。
鉄筋コンクリート造のマンションについては耐震基準が大きく変化しませんでしたが、木造住宅の耐震性能は向上しています。
実際どのくらいの地震であれば耐えられるのか

では、実際どのくらいの地震であれば耐えられるのでしょうか?
その点が、お客様にとっても関心のある部分でしょう。
結論からお伝えすると、新耐震基準は震度5程度なら建物が損傷しない、震度6〜7程度でも崩壊や倒壊はしないことを基準にしています。
さらに、新耐震基準は建物内の人命を守ることを基準として設けています。
ちなみに、旧耐震基準は震度5程度の地震が発生しても建物が崩壊しないことを目標に制定されました。
日本の耐震基準は世界的にもレベルが高く、進化し続けています。
耐震基準を確認したほうがいい理由

耐震基準を確認したほうがいい理由は、大きく2つあります。
- 耐震性が高いかどうか判断できる
- 住宅ローン控除などを受けられる可能性がある
なぜ耐震基準を確認したほうがいいのか説明できるか否かで、お客様の納得度も変わります。
耐震基準は住宅を選ぶ際の判断基準にもなるので、しっかりと説明できるようにしておきましょう。
耐震性が高いかどうか判断できる
耐震基準を確認すると、耐震性が高いかどうか判断できます。
耐震性の高い家に住めば、もし大規模な地震が起きたときでも、人命や財産を守れる可能性が高まります。
日本は地震大国なので、耐震性の高さはもはや必須といえるかもしれません。
しかし、耐震基準を確認しなければ耐震性が高いかどうかわかりません。
耐震性が高いかどうか判断するためにも、耐震基準は確認したほうがよいでしょう。
住宅ローン控除などを受けられる可能性がある
現行の耐震基準に適合していると、中古住宅でも住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
さらに、新耐震基準を満たしていれば、不動産取得税の軽減措置を受けられるかもしれません。
いずれにしても、耐震基準を確認しなければ住宅ローン控除や税制優遇を受けられるかの判断がつきません。
お客様は、住宅ローン控除や税制優遇措置を受けられるかどうかを重要視しているケースがあります。
耐震基準を把握しておき、さまざまな制度が活用できる可能性があることを伝えられるとよいでしょう。
旧耐震基準か新耐震基準か確認する方法

旧耐震基準か新耐震基準か判断するためには、建築確認通知書を確認しましょう。
建築確認通知書は、建築するときに提出した建築確認申請に書いた内容が、建築基準法の規定を満たしているか確認した旨を特定行政庁から建築主へ通知する書面です。
建築確認通知書に書かれている建築確認申請が受理された日が、1981年6月1日以降であれば新耐震基準が適用されていることがわかります。
ちなみに、日付が2000年6月1日以降であれば現行の耐震基準が適用されています。
また、1981年5月31日以前に建築されたものでも、耐震適合証明書があれば新耐震基準に適合しているため安心です。
耐震基準を確認するときの注意点

ここまで耐震基準について確認してきましたが、実は注意点があります。
新耐震基準かどうかを竣工日で判断してはいけません。
新耐震基準かどうかが決まるのは、竣工日ではなく建築確認申請がいつ実施されたかだからです。
たとえば、新耐震基準が施行された1981年6月1日以降に建物が完成していても、建築確認申請の日付が1981年5月31日であれば旧耐震基準の建物である可能性があります。
耐震基準を確認するときは、竣工日ではなく建築確認申請の日付であることを覚えておいてください。
構造計算のことならMake Houseにご相談ください
建築基準法の改正により、耐震基準は何度も変わってきました。
これまでに三度の改正があり、2000年からは今の耐震基準が適用されています。
耐震基準をチェックすれば、耐震性が高いかどうかを判断できるのはもちろんのこと、さまざまな優遇措置を受けられる可能性があることを確認できます。
地震大国である日本においては、耐震基準の確認はもはや必須でしょう。
お客様が気になるポイントの一つでもあるので、しっかりと説明できるようにしておいてください。
Make Houseは、工務店に特化した設計サポートを実施しています。
集客にお困りの場合は、いつでもご相談ください。
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
.png)
