「2025年のGX ZEHって、ウチの仕様で対応できるのか不安…」
「基準に乗り遅れると、集客や補助金で不利になるかも…」
そんな不安を抱えている工務店経営者の方も多いのではないでしょうか。
2025年からZEH基準が大きく見直され、今後は今までの施工仕様や提案内容では対応できないケースも出てきます。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
今後の対策として、ぜひご一読ください。
- GX ZEHとは?
- ZEH・Nearly ZEH・ZEH Readyの違い
- ZEH+と次世代ZEH+(LCCM住宅)で実現する未来の暮らし
GX ZEHとは?

2027年4月から新たに適用される住宅の省エネ基準について、戸建住宅を中心に大きな見直しが行われます。現行のZEH基準から、より高性能なGX志向型ZEH水準への移行が予定されており、工務店にとって今後の事業展開を検討する上で重要な情報となります。
ZEHの基本定義
ZEH(ゼッチ)とは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略で、住宅の省エネルギーと創エネルギーを組み合わせた次世代型の戸建て住宅のことです。
具体的には、断熱等級の向上により外皮性能を高めることで冷暖房のエネルギー消費を抑え、さらに高効率設備の導入によって大幅な省エネを実現します。
その上で太陽光発電などの再生可能エネルギーシステムを設置し、家庭で消費する一次エネルギー消費量と創り出すエネルギー量を相殺し、年間の正味エネルギー収支をゼロ以下にすることを目標としています。
経済産業省が2050年カーボンニュートラルを掲げる中、ZEHは環境に配慮した住宅の標準として期待されています。
GX ZEHの変更ポイント
2027年4月以降に導入が予定されている新しいZEH基準では、現行よりも性能要件が大幅に強化されます。
主な変更点の一覧:
1. 断熱性能の強化
現行は等級5ですが、新基準では等級6以上へと引き上げられ、外皮平均熱貫流率(UA値)のさらなる低減が必要となります。
2. 省エネ率の引き上げ
現行では一次エネルギー消費量20%以上削減でしたが、新基準では35%以上削減(再生可能エネルギーを除く)が条件となり、より高効率な省エネ設備の導入が必須条件となります。
3. エネルギーマネジメントの必須化
HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の設置が必須となり、定置用蓄電池の導入とHEMSによる充電制御が必要です。将来的なEV(電気自動車)との連携(V2H)も視野に入れられています。
4. 新築・改修・リフォームへの適用
新規建設の戸建住宅および集合住宅が主な対象となります。既存住宅ストックの改修・リフォーム事業にも支援制度を検討中で、2030年に向けた段階的な水準向上の方針が示されています。
この新基準により、GX志向型住宅と同水準の高性能基準がZEHに標準化され、住宅のエネルギー自立性と持続可能性が一層高まることが期待されています。2025年から準備を開始し、2027年の本格適用に備えることが重要です。
GX志向型住宅について以下のコラムも参考にしてください。
>【補助金160万円?】GX志向型住宅とは?工務店がお客様に提案すべき補助金の詳細や要件を徹底解説
>GX志向型住宅の基準とは?メリットやデメリットまで徹底解説
>GX志向型住宅の条件とは?補助金は最大で160万円受け取れる?
>長期優良住宅とGX志向型住宅の違いは?認定条件をわかりやすく解説
GX ZEHで可能な提案方法

新しいZEH基準に関する情報を正確に把握することで、工務店は顧客に対してより説得力のある提案が可能になります。
省エネ性能を数値で示す提案
GX ZEHでは、断熱等級や一次エネルギー消費量といった性能要件が明確な数値で定められています。
工務店がその内容を理解し、具体的なデータを提示しながら説明すれば「このプランなら補助金や支援制度の対象になります」と根拠を持って提案できます。
数値に裏打ちされた説明は説得力が高く、問い合わせから契約に至る率の向上も期待できるでしょう。
さらに、省エネ効果のシミュレーション資料をグラフ化して見せれば、専門性と信頼感を一層強調することが可能です。
補助金・税制優遇を組み合わせた資金提案
ZEH基準を満たす住宅は、国の補助金や住宅ローン控除、グリーン住宅ポイントといった優遇制度を利用できる点が大きなメリットです。
工務店が「初期費用は上がりますが、支援制度を活用すれば実質負担は軽減できます」と伝えれば、費用面での不安がぐっと減ります。
資金計画を含めた具体的な提案は、長期的なコストパフォーマンスを実感してもらう強力な材料になり、加えて、将来的なエネルギー価格高騰リスクを回避できる点や、2030年に向けたさらなる省エネ化の流れに対応できる点も、顧客にとって大きな安心材料となるでしょう。
断熱・設備仕様を選択肢として提案
新基準を踏まえると、断熱材の種類や厚み、窓の性能区分、さらには太陽光発電や高効率設備、蓄電池やHEMSの有無まで、複数の仕様を比較提案できます。
「快適性を優先するか、コストを抑えるか」「今すぐ全て満たすか、将来の改修で対応するか」を顧客自身が選択できるため、納得度の高い住まいづくりにつながります。
選択肢を提示できる工務店は、顧客にとってより信頼されるパートナーとなるでしょう。
また、仕様の違いによる年間光熱費や快適性の変化を、セミナーや商品説明会で可視化すれば、判断材料としてさらに有効です。
>GX志向型住宅の条件とは?補助金は最大で160万円受け取れる?
ZEHの種類は1つじゃない!ZEH・Nearly ZEH・ZEH Readyの違いを徹底比較

ZEHには、地域や条件に応じた複数の区分が用意されています。それぞれの定義と要件を理解し、適切な提案を行うことが重要です。
Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)
Nearly ZEHは、ZEHの達成が難しい地域向けに設けられた区分です。
寒冷地や多雪地、敷地面積が限られる都市部など、日射量や太陽光パネル設置面積を確保しにくいエリアが主な対象となります。
断熱性能や省エネ性能(一次エネルギー消費量20%以上削減)は通常のZEHと同等ですが、創エネを含めた削減率は「75%以上100%未満」と緩和されています。地域の気候条件に応じた柔軟な対応が可能です。
Nearly ZEHの名称は、「ほぼZEH」という意味を持ち、地域特性を考慮しつつ、ZEHに近い省エネ住宅を実現できるのが大きなメリットです。
ZEH Ready(ゼッチ・レディ)
ZEH Readyは、将来的に再生可能エネルギー発電システムを導入することを前提とした住宅区分です。
創エネ設備の設置が現時点では必須ではなく、断熱性能と高効率な省エネ設備のみで、一次エネルギー消費量を50%以上削減できることが条件となります。後から太陽光パネルや蓄電池を設置することで、完全なZEHへ移行可能です。
ZEH Readyの型は、コストやタイミングに応じた段階的な導入を目指す方法として有効です。
なお、GX ZEHの定義上では”Ready”よりも”Oriented(志向型)”が主な区分として用いられる予定です。
参照:資源エネルギー庁
ZEHを超える性能!ZEH+と次世代ZEH+(LCCM住宅)で実現する未来の暮らし

より高い性能水準を目指す住宅として、ZEH+シリーズやLCCM住宅という区分も用意されています。
ZEH+(ゼッチ・プラス)の達成要件
ZEH+は、標準的なZEHをさらに進化させた上位グレードの住宅です。
- 一次エネルギー消費量:25%以上削減(ZEHより5%向上)
- 太陽光発電などによる創エネで年間の正味エネルギー収支をゼロに
- 以下3項目のうち2つ以上を満たす必要あり:
- 外皮性能のさらなる強化(UA値の低減)
- 高度エネルギーマネジメント(HEMSによる制御の高度化)
- 電気自動車(EV)との連携(V2Hシステムの導入)
ZEH+は、省エネと創エネの自家消費率を向上させることを目標としており、補助金額もZEHに比べて高い水準となります。将来の環境性能を見据えた住宅として、セミナーや説明会での紹介も効果的です。
参照:環境省
次世代ZEH+(LCCM住宅)の達成要件
LCCM(Life Cycle Carbon Minus)住宅は、居住中のエネルギー収支に注目するZEHやZEH+とは異なり、建設から廃棄に至るライフサイクル全体を通じたCO2排出量をマイナスにすることを目指した最高水準の住宅です。
- ZEH+と同様に一次エネルギー消費量25%以上削減を満たす
- 再生可能エネルギーによる創エネで、建設時や廃棄時に発生するCO2まで相殺
- CASBEE(建築環境総合性能評価システム)におけるライフサイクルCO2の基準をクリアし認定を取得
LCCM住宅は、2050年カーボンニュートラルを掲げる日本において、環境負荷を最小限に抑えた住宅の理想形といえます。平屋から多層階まで、幅広い住宅型に適用可能な制度として、今後の普及が期待されています。
参照:国土交通省
まとめ
ZEHは単なる省エネ住宅ではなく、2027年以降の住宅建設における標準となる基準です。
新しい要件を早めに把握し、顧客に安心して任せてもらえる提案を用意しておくことが重要です。
今後の対応ポイント:
- 2025年から準備を開始し、2027年4月の本格適用に備える
- 現行基準と新基準の違いを正確に理解し、資料やセミナーで説明できる体制を整える
- 断熱等級、省エネ率、HEMS、蓄電池など、全ての性能要件を満たす施工方法を検討
- 補助金や支援制度の情報を常に更新し、顧客への問い合わせに適切に対応
- 新築だけでなく、改修・リフォーム事業での活用も視野に入れる
変化を恐れるのではなく、新しい制度に対応できる体制を整えることで、地域で信頼される工務店へと成長できるはずです。
基準対応を先取りする姿勢が、長期的なブランド価値を築くことにつながるため、今のうちに新ZEHに関する情報を深く理解しておきましょう。
※本記事の内容は2025年9月26日時点の情報に基づいています。最新の制度詳細については、経済産業省や関連省庁の発表をご確認ください。
【無料】
『GX ZEH』の入門書
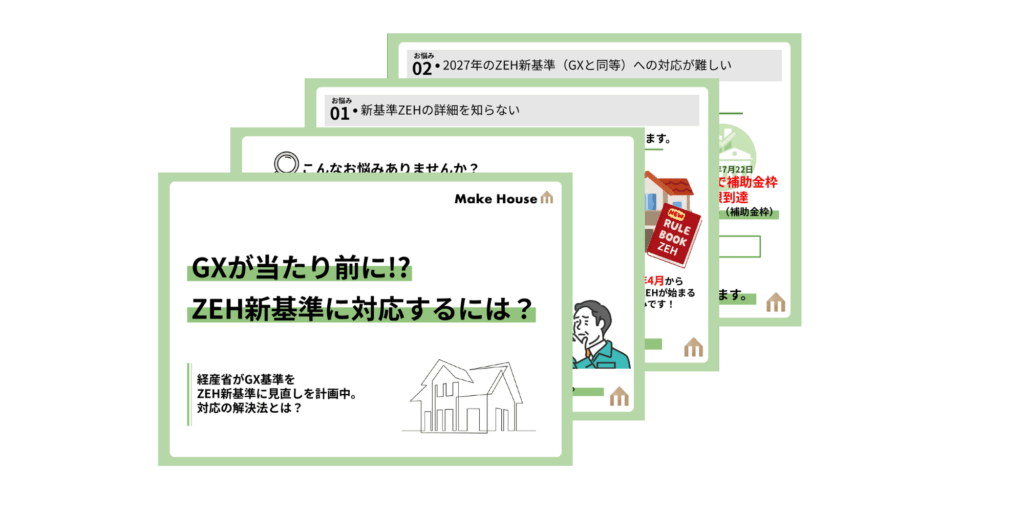
・GX ZEHの詳細を知らない…
・GX ZEHへの対応が難しい…
・GX対応しても高コストで値段が落ちない…
\上記のようなお悩みのある工務店様は今すぐチェック/
.png)
