「ZEHの基準が変わるって聞いたけど、具体的に何がどう変わるの?」
「最新基準に対応しないと、提案の幅が狭まってしまうかも…」
このように考えている工務店関係の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2025年のZEH基準見直しに伴い、断熱性能や一次エネルギー消費量の算定方法など、これまでとは違うポイントが求められるようになります。
特に工務店にとっては、設計・提案の段階でこれらを正しく理解しておくことが不可欠です。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
- なぜ今、基準の強化が必要なのか?
- ZEH基準見直しの歴史と最新の適用時期
- 新ZEH基準の4つの重要変更点
【無料】
『GX ZEH』の入門書
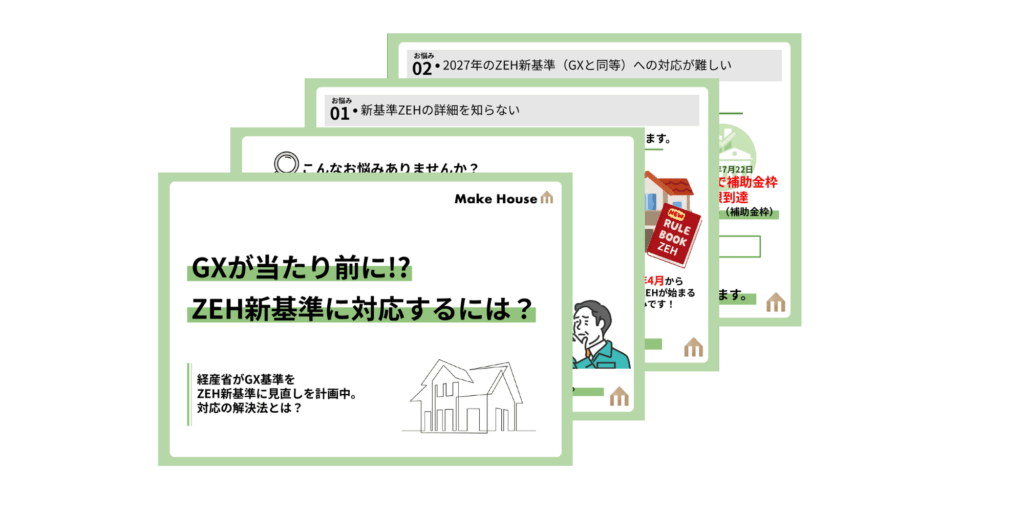
・GX ZEHの詳細を知らない…
・GX ZEHへの対応が難しい…
・GX対応しても高コストで値段が落ちない…
\上記のようなお悩みのある工務店様は今すぐチェック/
ZEH基準見直しの背景:なぜ今、基準の強化が必要なのか?

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、住宅の省エネ性能強化は避けられない課題です。
2025年度から新築住宅に「省エネ基準適合義務化」が適用され、より高性能な住宅が求められます。
加えて、近年のエネルギー価格高騰は家庭での自給自足の必要性を高めており、今回の基準見直しは規制強化にとどまらず、持続可能な社会を実現する大きな一歩といえるでしょう。
【いつから?】ZEH基準見直しの歴史と最新の適用時期

日本の省エネルギー基準は1980年に制定されて以降、度々改正され、強化されてきました。
2015年にZEH基準が制定され、断熱等性能等級5が要件とされました。
しかし、初期のZEH基準は断熱性能の要求水準が比較的低く、大容量の太陽光発電システムを搭載すれば達成可能であるという課題が指摘されていました。
そこで、ZEHの省エネ性能をさらに高め、自家消費の拡大を目指す「ZEH+」の定義が2018年5月に公表されました。
その後、断熱等性能等級6以上などを満たす「ハイグレード仕様」が交付決定の過半数を占めたことなどを背景に、ZEH+の定義が見直されました。
また、2025年5月に資源エネルギー庁が公表した方針により、ZEH基準がさらに強化されることになりました。
新しいZEH基準による認証は2027年4月から開始される予定で、断熱性能の強化、一次エネルギー消費量削減率の引き上げ、設備の導入要件追加などが盛り込まれます。
【何が変わる】新ZEH基準(GX ZEH)の4つの重要変更点をご紹介

新ZEH基準(GX ZEH)の4つの重要変更点を徹底比較の上で、解説します。
変更点①:断熱性能(UA値)の基準がより厳しくなる
新しいZEH基準では、住宅の断熱性能を示す「断熱等性能等級」が現行の等級5から等級6へと引き上げられます。
これは、壁や窓など外皮から逃げる熱の量を表すUA値を、より低い水準に抑えることを求めるものです。
例えば、比較的温暖な6地域でもUA値0.46以下が条件となり、従来よりも高性能な断熱材やトリプルガラスのサッシがほぼ必須となります。
太陽光発電に依存するのではなく、建物自体の性能を根本的に高めることが狙いです。
変更点②:省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率)の強化
新基準では、冷暖房や給湯といった一次エネルギー消費の削減率が、現行の20%以上から35%以上へと大幅に引き上げられます。
BEI値が0.8以下から0.65以下へ強化され、GX志向型住宅と同等の厳しさとなります。
※BEI(ビーイーアイ)値:「Building Energy Index」の略称で、建築物のエネルギー消費効率を示す指標
この条件を満たすには、断熱強化だけでなく、高効率なエアコンや給湯器、熱交換型換気システムといった先進設備の導入が欠かせません。
住宅全体で省エネ性能を底上げすることが不可欠です。
変更点③:蓄電池の設置が実質必須になる
新ZEH基準では、戸建住宅における蓄電池設置が事実上必須とされます。
背景には、売電価格の下落により、発電電力を自家消費する方が経済的メリットを生むようになったことが挙げられます。
蓄電池を導入することで、昼間の発電を夜間に活用でき、災害時には非常用電源としても利用可能です。
これにより、自給自足のエネルギー活用が進み、利便性も高まります。
変更点④:高度なエネルギーマネジメント(HEMS)の導入が必要
新基準では、家庭内のエネルギーを効率的に管理するためHEMSの導入が要件化されます。
HEMSは単なる使用状況の可視化にとどまらず、蓄電池やエアコン、給湯器を連動させ、自動的に最適なエネルギー制御を実現します。
さらに、需要のピークを避けて充電するといった対応も可能です。
これにより、家庭内の省エネ効果を最大化し、持続可能な暮らしを支える仕組みが実現するでしょう。
ZEH基準の見直しが家づくりに与える3つの影響

ZEH基準の見直しが家づくりに与える3つの影響について解説します。
影響①:建築コストは上がる?初期投資とランニングコストの最適解
高性能設備や断熱材の導入で、初期費用は上昇傾向にあります。
しかし、光熱費削減によって長期的には十分回収でき、ライフサイクルコストで見ればむしろお得になる可能性が高いです。
加えて、国の補助金制度を活用すれば初期投資の負担を軽減できます。
家づくりでは目先の建築費だけでなく、生涯コスト全体を見据えた判断が欠かせません。
影響②:住宅の「快適性」と「資産価値」が大きく向上
高断熱・高気密の住宅は、冬でも家全体が暖かく、夏も涼しい快適な環境を実現します。
温度差によるヒートショックのリスクを減らし、家族の健康維持にもつながります。
また、省エネ性能はBELSなどで数値化され、不動産の資産価値向上に直結。
エネルギー価格の変動に強い住宅は、安心と経済性を両立できる魅力ある住まいといえるでしょう。
影響③:ハウスメーカー・工務店選びの重要性が格段にアップ
新基準対応には、高度な設計と施工技術を持つ住宅会社の選択が不可欠です。
ZEH実績の豊富さや補助金制度への知識、UA値やC値を公開しているかなどを確認することが求められます。
性能・デザイン・コストのバランスを取りながら、施主の希望に寄り添える会社を選ぶことで、満足度の高い家づくりが実現します。
まとめ:ZEH基準の見直しは、未来の「当たり前」の家づくりへの第一歩
今回のZEHに関する見直しは、快適で経済的かつ環境に優しい住宅を社会の標準とするための大きな転換点です。
初期費用の増加はあるものの、補助金活用や光熱費削減によって十分カバーできます。
未来の暮らしを見据えるなら、新ZEH基準に適合した家づくりこそが賢明な選択です。
この新ZEH基準を理解しておくことで、顧客に対してより提案しやすくなります。
今回の記事を読み返し、新ZEH基準の内容を今から理解しておきましょう。
【無料】
『GX ZEH』の入門書
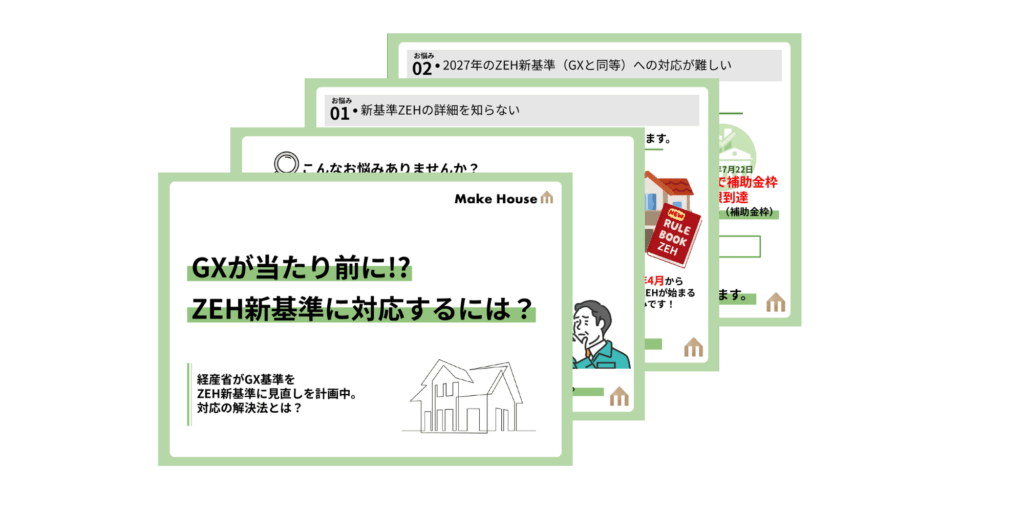
・GX ZEHの詳細を知らない…
・GX ZEHへの対応が難しい…
・GX対応しても高コストで値段が落ちない…
\上記のようなお悩みのある工務店様は今すぐチェック/
.png)
