2025年4月に建築基準法の改正が行われました。
この法改正により、建築確認申請は手間が増えることが予想されています。工務店の負担は今以上に大きくなるでしょう。
また、大規模リフォームには建築確認が必要かご存知ですか?施工箇所別にお伝えするので、ぜひこの機会に確認しておきましょう。
この記事では、2025年4月から建築確認申請がどうなるのかについて詳しく解説します。
今回の法改正で押さえておきたいポイントも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
- 法改正により建築確認申請はどう変わるのか
- 大規模リフォームには建築確認申請が必要なのか
- 今回の法改正で押さえておきたいポイント
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
そもそも建築確認申請とは?

建築確認申請は、建築基準法や条例に適合した建物であるかの確認を受けるために必要な申請です。
新築工事や大掛かりな増改築工事などに着手する前に、必要な書類を整えて確認検査機関や特定行政庁に提出します。
違法な建築物を排除する目的で運用されているルールです。
建築確認は着手前に申請書を提出しますが、工事完了後も審査が実施されるため注意が必要です。
おおむね以下の流れの中で、建築確認は実施されます。
- 設計
- 事前相談、ヒアリング
- 建築確認申請
- 建築確認検査機関や特定行政の審査
- 建築確認済証の発行
- 工事着工
- 工事完了
- 工事が完了した旨の届出
- 検査
- 検査済証の発行
建築確認申請の基本的な流れを把握しておくと、お客様への説明もスムーズに進むでしょう。
2025年の建築基準法の改正により建築確認申請はどうなる?
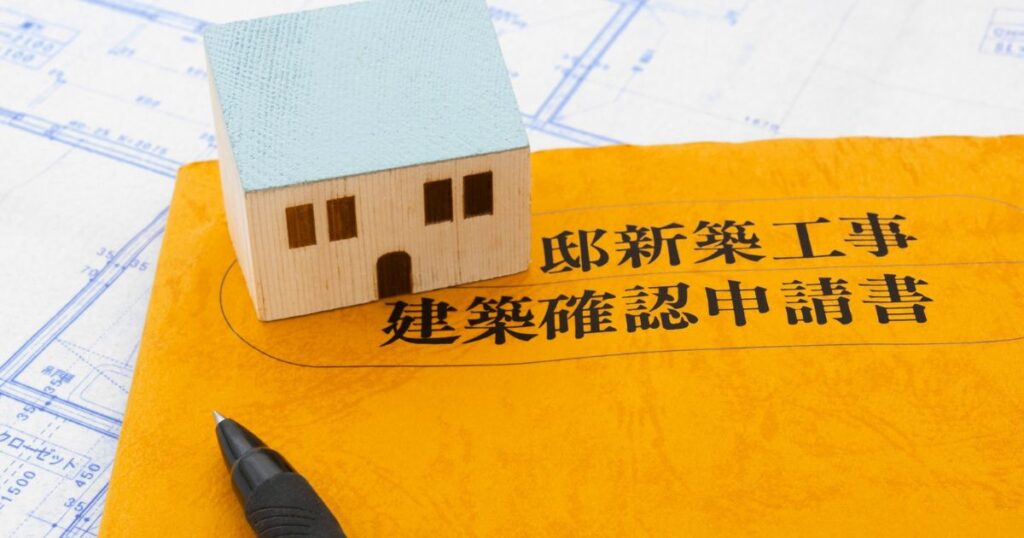
2025年の建築基準法の改正により、建築確認申請の手間が増える可能性があります。
建築確認申請は新築住宅のみならず、リフォームを行う際にも必要です。
建築物の設計図、構造計算書などを用意して安全性や適法性の確認を受けるのですが、工務店は作業が増えて負担が増えることも覚悟しておきましょう。
また、建築確認にかかる時間やコストが大きくなれば、それは建築コストの増加につながります。
結果、お客様が住宅を建てるときの費用が増加する恐れがあるため注意が必要です。
建築基準法で押さえておきたい部分として、以下をチェックしておきましょう。

大規模リフォームには建築確認申請が必要?
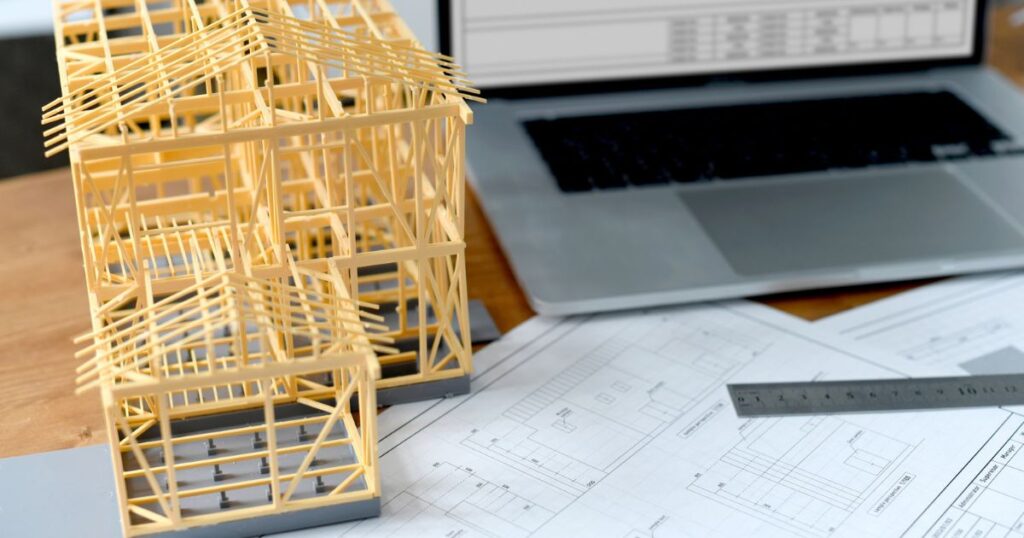
2025年4月の法改正で建築確認申請の負担が大きくなることはわかりましたが、大規模リフォームには影響があるのでしょうか?
大規模リフォームで建築確認申請が必要かどうか、施工箇所別に見ていきましょう。
屋根のリフォーム
屋根のリフォームの場合、屋根材を交換するときに構造材の工事も行い、かつその施工箇所の面積が全体の過半を占めるケースでは建築確認申請が必要です。
たとえば、傷んでいる化粧スレートを交換するタイミングで下地の合板あるいは屋根を構成する部分の工事を実施し、さらにその施工した箇所の面積が全体の過半を占めているケースです。
一方で、屋根材とその直下にある防水シートで工事が終了するケースでは、建築確認申請は必要ありません。
構造材を直接施工せず、カバー工法で施工するケースも不要です。
外壁のリフォーム
外壁のリフォームは、構造部も含めて改修を行い、外壁全体の過半を工事するときに建築確認申請が必要です。
簡単に言えば、外壁を壊して作り直すリフォームは建築確認申請をしなければなりません。
ほかにも、仕上げ材だけを改修する場合でも、それが外壁全体にわたるなら建築確認申請をします。
ただし、外壁の内側から断熱改修をするときは建築確認申請は不要です。
床の張り替え
床を構成する根太、梁といった構造材を含む床の張り替えは建築確認申請が必要です。
床の面積の過半におよぶ大規模リフォームだと判断されると、建築確認申請をしなければなりません。
ただし、フローリングなど床の仕上げ材だけを施工するケースでは建築確認申請は必要ありません。

建築確認申請に影響を与える法改正で押さえておきたいポイント
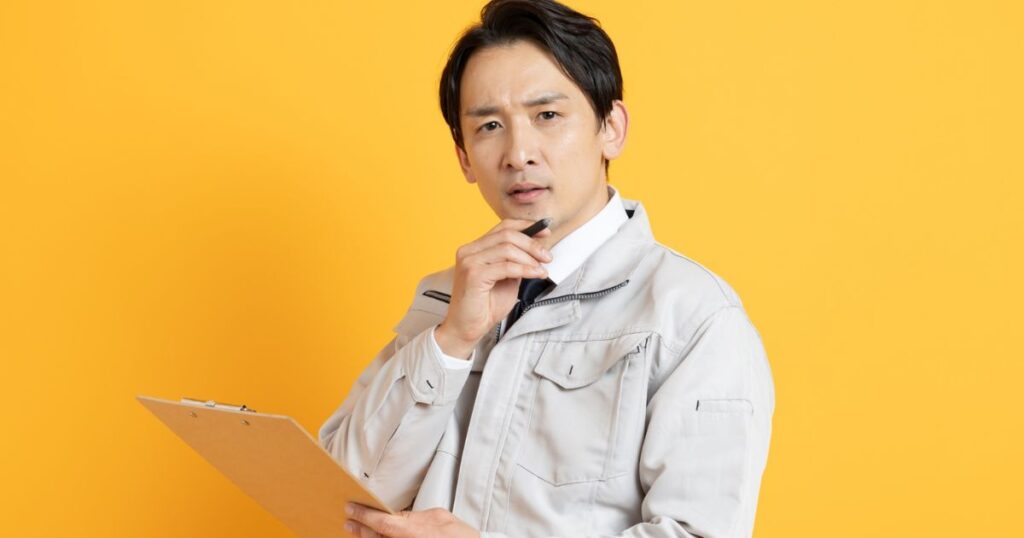
建築確認申請に影響を与える法改正で押さえておきたいポイントは、大きく6つあります。
- 4号特例の縮小
- 構造規則の合理化
- 省エネ基準の義務化
- 大規模木造建築物の防火規定変更
- 中層木造建築物の耐火性能基準合理化
- 既存不適格建築物現行基準の一部免除
以下でそれぞれの詳細を確認しましょう。
4号特例の縮小
今回の法改正で最も注目されたのが、4号特例の縮小です。
従来4号建築物の区分にあった建物は、新2号建築物と新3号建築物に再編されました。
もともとの4号建築物は、建築士が設計していたり、工事監理者が設計図書のとおりに施工されていることを確認したりしていれば、一部の審査を省略できるといった利点がありました。
しかし、今回の法改正で基本的に審査が必要となり、建築確認申請時に提出する書類も増えています。
4号特例のまとめ記事を以下に用意しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
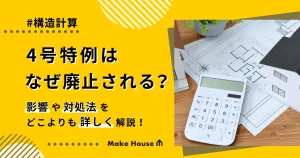
構造規則の合理化
今回の法改正では、構造規制が合理化されました。
法改正後は3階以下かつ高さ16m以下の木造建築物は簡易な構造計算で建築できるようになっています。
これは、高層化が続く木造建築物をスムーズに建てる目的で改正されたルールです。
ただし、構造計算が必要だと判断される延べ面積の要件は縮小されたので注意が必要です。
従来500平方メートルだったのが、法改正後は300平方メートルになりました。
省エネ基準の義務化
省エネ基準の義務化も押さえておきたいポイントの一つです。
従来は届出義務や説明義務だった建築物も、基準への適合が必須となるので、依頼主への丁寧な説明が必要になるでしょう。
また、増改築する際は、その部分のみ省エネ基準をクリアしていれば問題ありません。
詳しい部分は以下の記事で解説しています。

大規模木造建築物の防火規定変更
大規模木造建築物の防火規定変更も法改正のポイントとして押さえておくとよいでしょう。
防火規定の変更で、内装の自由度が増すという恩恵を受けられました。
実際、木造の露出をうまく活用したデザインもできるようになっています。
しかし、火災対策として防火区画の強化は求められることになります。
中層木造建築物の耐火性能基準合理化
今回の法改正では、中層木造建築物の耐火性能基準の合理化(緩和)が行われた点も覚えておきたいところです。
法改正後は、別区画部分が90分耐火性能を保てると、木造建築可の判断がくだされます。
このルール改正により、集合住宅や商業施設で積極的に木造が利用されることになるかもしれません。
既存不適格建築物現行基準の一部免除
今回の法改正では、既存不適格建築物の現行基準の一部が免除となりました。
既存不適格建築物は、従来の基準はクリアしていたが、その後現在のルールには適合しなくなった建物のことを指しています。
今回、条件をクリアすれば現行のルールを適用しなくてもいいという免除規定が設けられました。
これは、空き家問題や既存ストック住宅の再利用を促す目的があります。
接道義務に反している土地でもリノベーションを行えるようになったので、築年数の古い建物の再利用が促進される可能性はあります。
建築確認申請に関するよくある質問

建築確認申請に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 4号特例廃止はいつからですか?
- 構造計算が義務化されるのは2025年以降ですか?
よくある質問に目を通すことで、今回の法改正に対する理解も深まります。
一つずつ回答を見ていきましょう。
4号特例廃止はいつからですか?
4号特例の廃止は、2025年4月です。
厳密には廃止ではなく縮小ですが、今回の建築基準法の改正により実施されました。
4号特例の縮小により、以下の変更がありました。
- 建築確認および検査、審査省略制度の対象範囲が変わった
- 建築確認申請時に、構造および省エネ関連の図書の提出が必要になった
4号特例の廃止については、以下の記事をご覧ください。
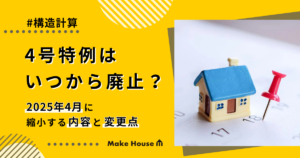
構造計算が義務化されるのは2025年以降ですか?
構造計算が義務化されるのは、2025年4月です。
今回の法改正で適用となりました。
構造計算については、専門的な知識やノウハウが必要です。
簡単に習得できるものでもないので、外注も視野に入れながら対応を検討しましょう。
構造計算の義務化は、以下の記事で詳細をチェックしてみてください。
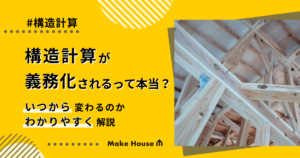
構造計算のことならMake Houseにご相談ください
2025年の建築基準法改正により、建築確認申請の負担が大きくなる可能性があることがわかりました。
そして、建築確認申請にかかる時間や手間が増えれば、建築コストも増加する恐れがあります。
お客様に丁寧に説明ができなければ、コストの増加による客離れも起きるかもしれません。
2025年4月の法改正については、ここでしっかり覚えておきましょう。
また、今回の法改正で構造計算が義務化されました。
構造計算についてお困りの場合は些細なことでも構いませんので、Make Houseにご相談ください。
早く、コスパよく構造計算を行う手法についての資料をご確認ください
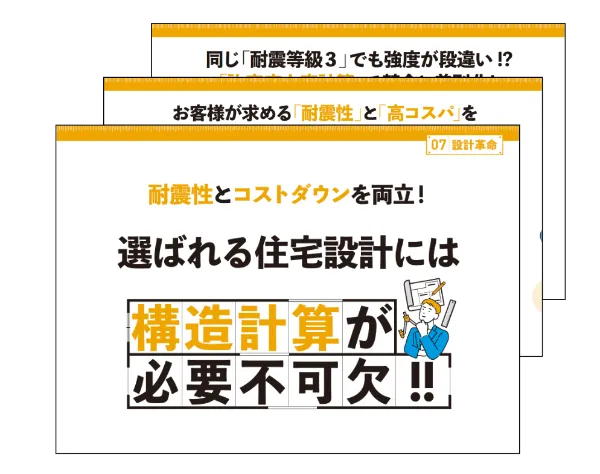
この資料でわかること
- 「耐震等級3」の計算方法による違い
- 耐震性が上がってもコストダウンできる方法
- 「耐震等級3」で差別化する方法
【注意事項】
本資料は個人・フリーランスの方等へのご提供を致しておりません。また、当社が同業他社と判断したお客様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
.png)
