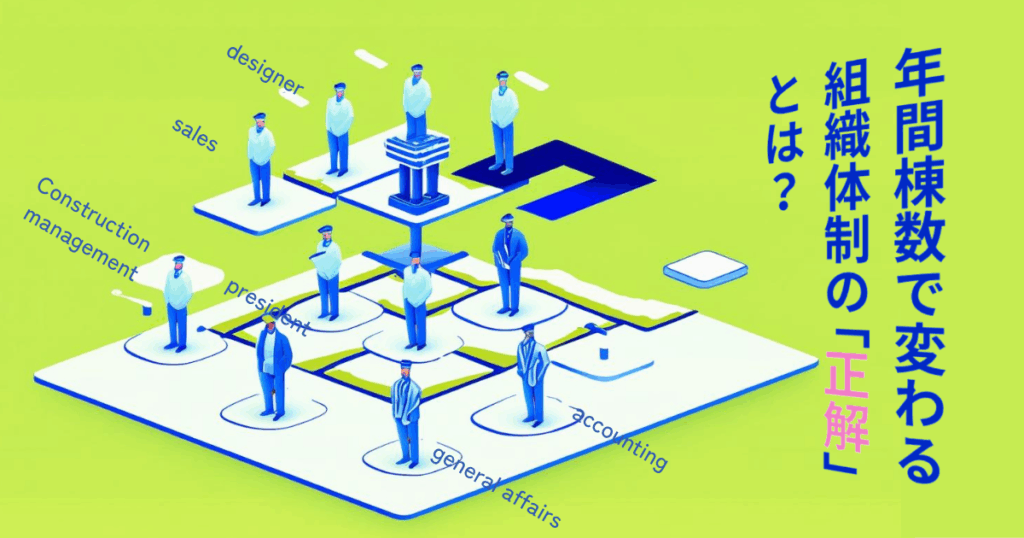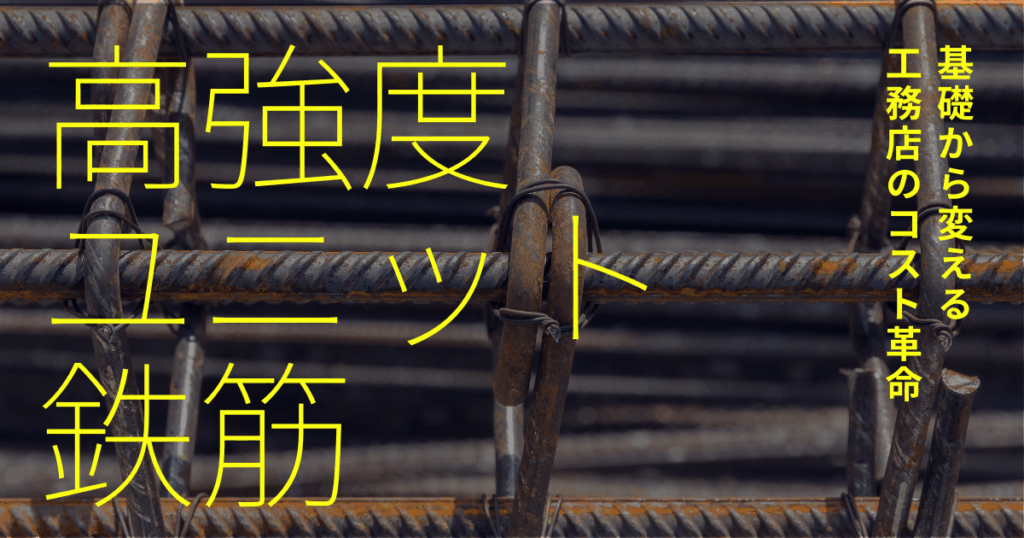2025年4月に建築基準法の大幅な改正が予定されています。
建築確認申請時の書類作成の手間やコストなど工務店においても大きく影響するため、法改正の内容を把握する必要があります。
そこで本記事では、建築基準法改正で家づくりはどう変わるかについて詳しく解説します。
改正内容も紹介するので、2025年の建築基準法改正についてお悩みの工務店経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること
- 建築基準法とは
- 2025年の建築基準法改正におけるポイント
- 2025年の建築基準法改正におけるメリット・デメリット
また、当社、Make Houseでは工務店に特化した設計に関するサポートを実施しております。
以下のリンクから無料でお客様に選ばれる設計に関する資料をダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
建築基準法とは?
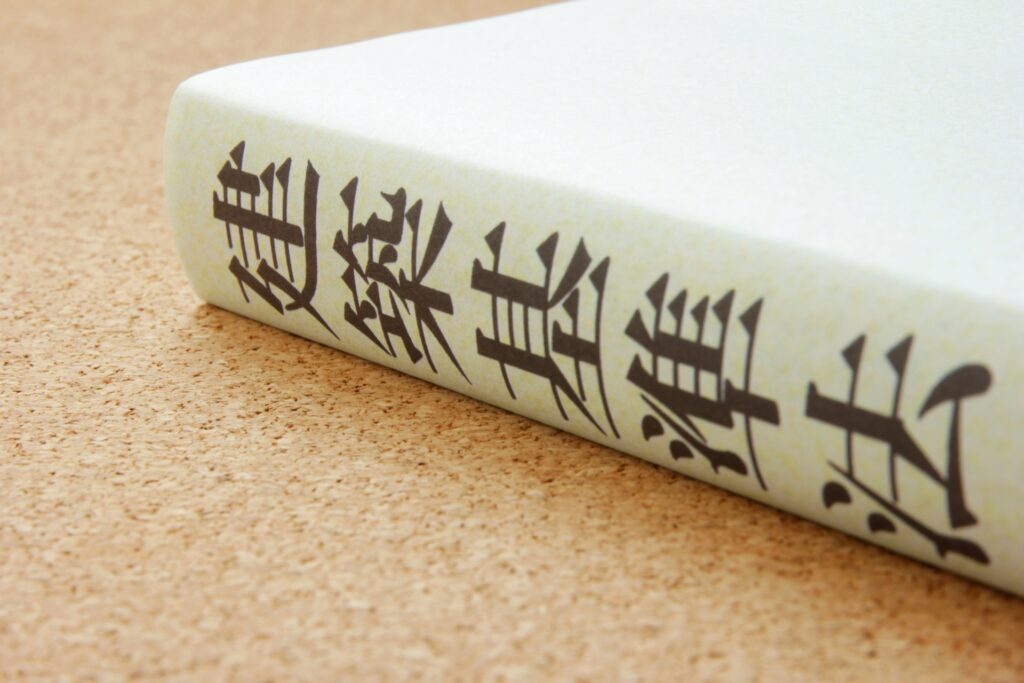
建築基準法とは、建物を建築する際の建築物の敷地や構造、設備、用途などに関する最低の基準を定めた法律のことです。建築物の安全を確保することによって、国民の生命・健康・財産の保護を図ることを目的としています。
実際に建物を建てる場合は、工事の着手前に建築主事の確認を受ける必要があります。
建築主事とは確認申請や完了検査の審査を行う公的な機関のことです。
建築基準法の代表的な項目
建築基準法には様々な項目がありますが、代表的なルールは、以下のとおりです。
| 代表的なルール | 内容 |
| 接道義務 | 建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければならない |
| 建ぺい率・容積率・高さ制限 | 敷地に対して建築できる建物の規模を制限する |
| 日影規制・斜線制限 | 既存建物の風通しや日照が確保できなくなることを防止する |
13種類に区分されたエリアごとに建築できる建物の種類や用途を制限する「用途地域」や、指定地域内の建築物では一定の防火性能や設備が必要になる「防火地域・準防火地域」は、都市計画法で定められているルールです。
建築基準法が改正される背景
2025年の建築基準法改正について、建築物の省エネ対策を加速させたいという背景があります。世界各国が取り組んでいるカーボンニュートラル2050を実現させるためには、建築分野での省エネ対策強化が必要なのです。
カーボンニュートラル2050とは、2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにすることを目標とする取組のことです。
2025年4月からは、原則としてすべての新築住宅に対して、省エネ基準の適合が義務化されることになり、2030年までにはZEH基準に水準を引き上げることも予定されています。
※ZEH基準:太陽光発電などを利用して家全体の消費エネルギーの収支をゼロにすることを目指す指標のこと。
2025年の建築基準法改正におけるポイント
2025年4月の建築基準法改正では様々な改正が予定されているため、工務店において影響がある項目について詳しく解説します。
4号特例の縮小
2025年の建築基準法改正では「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」が新設されます。
| 新2号建築物 | 木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超 |
| 新3号建築物 | 木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下 |
新2号建築物に該当する建物の場合は、構造計算審査の対象となります。構造計算審査とは建物の強度などが建築基準法に定められた基準以上であるかを確認する審査のことです。
これまで構造計算に対応していなかった工務店においては対策が必要となるでしょう。
以下の記事も参考になるので、ぜひチェックしてみてください。
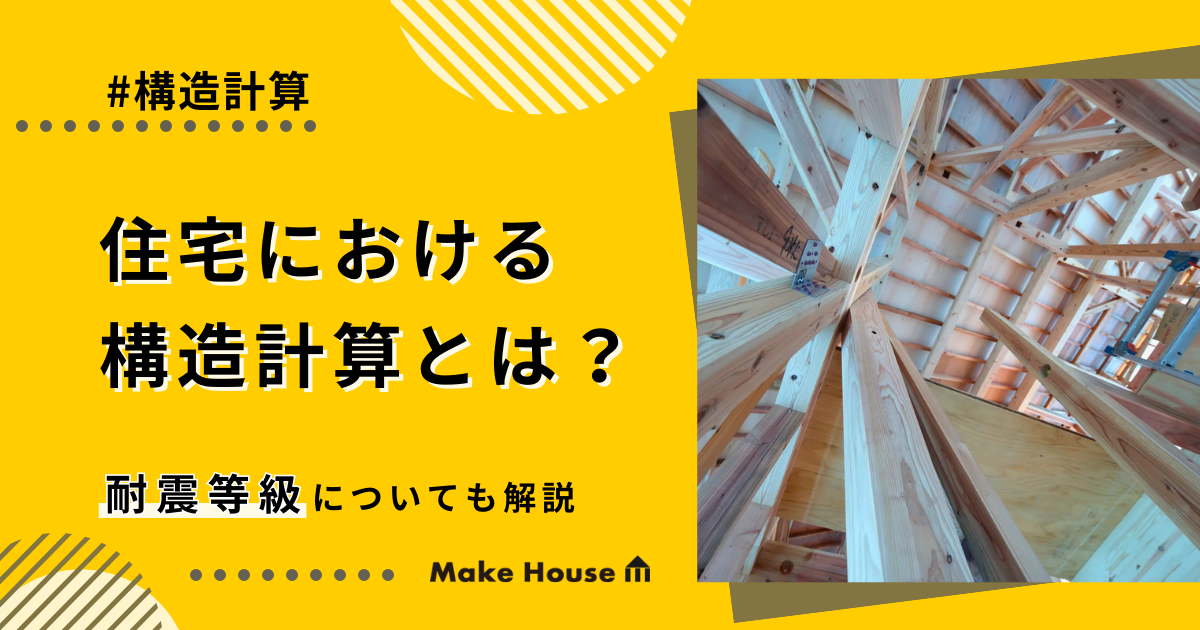
なお、当社、MakeHouseでは工務店に特化した設計におけるサポートを提供しております。
以下のリンクから無料でお客様に選ばれる設計に関する資料をダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
4号特例とは
4号特例とは、以下のような小規模な木造建築物を対象に建築確認で構造審査を省略する特例のことです。
- 「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
4号特例については、以下の記事で詳しくまとめています。
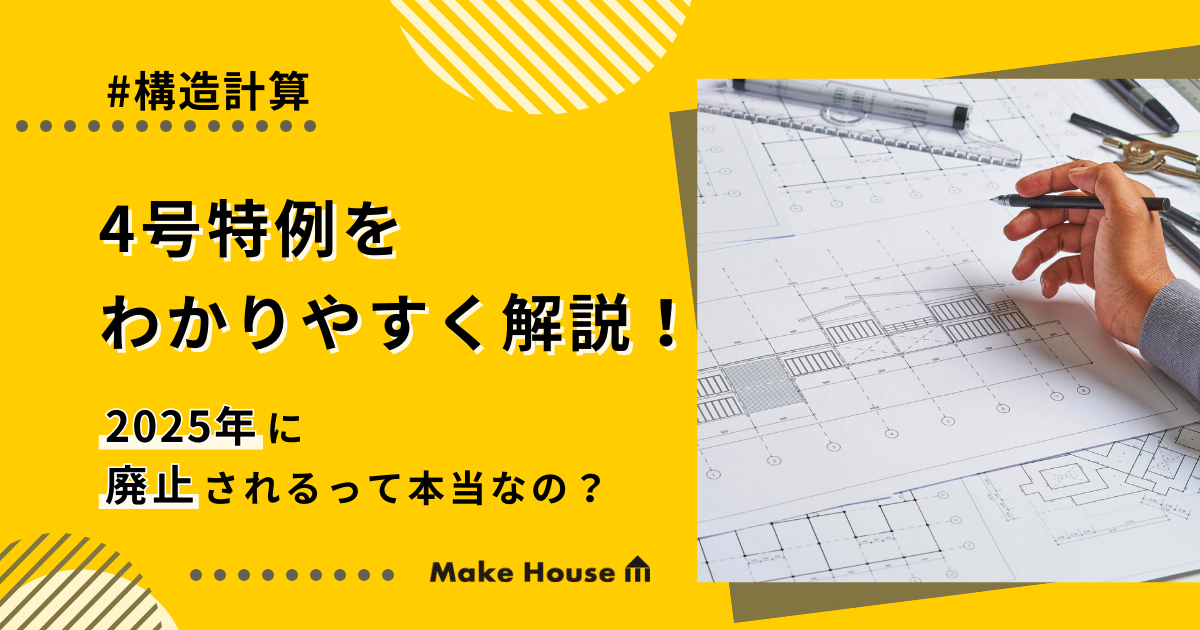
構造計算が必要な木造建築物が変更
現行の建築基準法では延床面積500㎡以下の木造建築物において、構造計算が義務化されていませんが、2025年4月の改正によって構造計算が必要な規模が「延床面積300㎡超」と引き下げられることになります。
平屋の場合は該当するケースが少ないかもしれませんが、延床面積が300㎡を超える場合は構造計算が必要になります。
壁量計算における必要壁量が増加
2025年4月の建築基準法改正では、壁量計算における必要壁量が現在のおよそ1.6倍必要になり、柱の小径についても、建物の重量に応じて求める計算式が盛り込まれることになります。
壁量計算を使用して在来工法の家を建てる場合は、大空間が作りにくくなる可能性があり、壁量を増やして太い柱を作る必要があるため、使用する材料が増えることによるコストアップが懸念されます。
以下の記事でわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
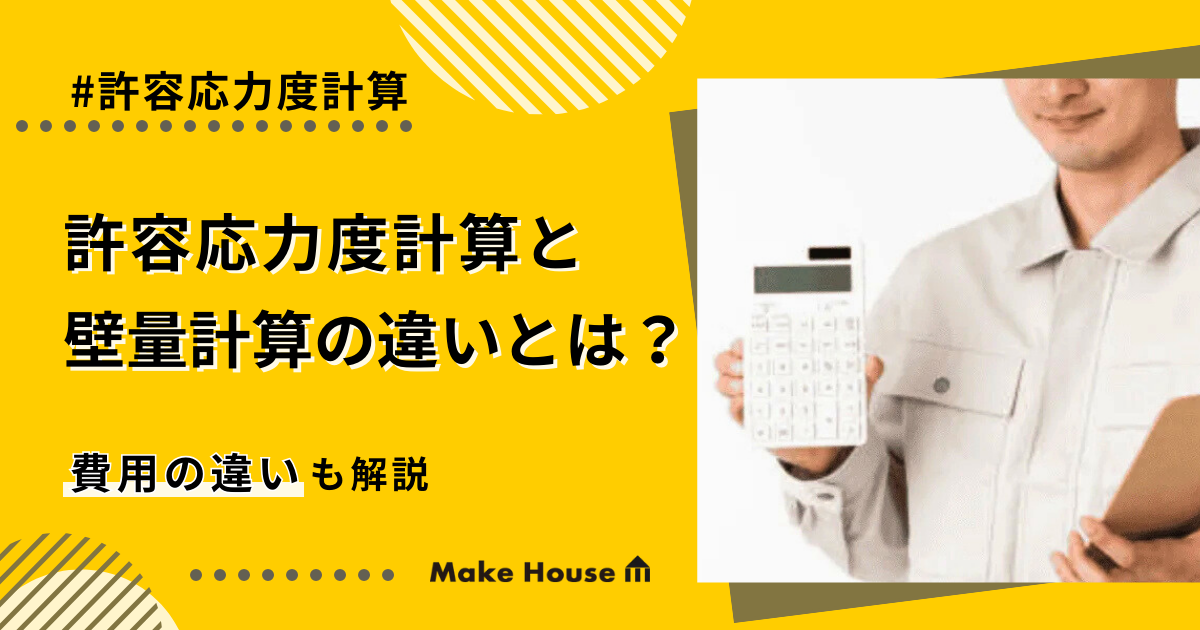
2025年の建築基準法改正におけるメリット・デメリット

2025年の建築基準法改正には、以下のようなメリットとデメリットが存在します。
メリット
2025年の建築基準法改正によって、建物を建てる際の基準が厳しくなるため、より安全性の高い構造の建物ができるため、お客様に喜ばれます。
また、先述のとおり、カーボンニュートラル2050の実現を目標としているため、建築物の省エネ対策が加速できれば、日本の環境問題への貢献度を高められるでしょう。
デメリット
4号特例の縮小によって、規模によっては建築確認申請に時間がかかり、コストも増加します。構造計算が必要になれば、自社で対応するか、外注するか対策を講じる必要があります。
また施工においても、審査や構造関連の資料の提出などによって施工期間が長くなる恐れもあります。
まとめ|構造計算であればMake Houseにお任せください!
今回の記事では、2025年の建築基準法改正について詳しく解説しました。法改正によって建物の品質は向上するためお客様にはメリットがありますが、建築確認申請には、これまで以上に時間と手間がかかり、コストも増加します。
当社では、お客様に選ばれるための設計についてノウハウを持っています。
なかなか設計でお客様にうまくアプローチできないと悩んでいる場合は、ぜひ以下のリンクから無料で資料をダウンロードしてみてください!
【無料】
『お客様に選ばれる』ための設計入門書

・お客様のニーズを捉えきれていない工務店様
・デザイン性の高い設計が苦手な工務店様
・高性能住宅を標準にしたい工務店様
\今すぐ知りたい方はこちら/
.png)