建築基準法において「4号建築物」と定義される小規模な建物の確認申請手続きは、2025年の改正による大きな変更が予定されています。
そこでこの記事では、4号建築物がどのようなものか、そしてこれまでの特例がどのように変わるのかをわかりやすく解説します。
また、新たに創設される新2号建築物と新3号建築物の違いとは何か、そしてこれらの変更がいつから施行されるのかについても詳しくお伝えします。
この記事のポイント
目次
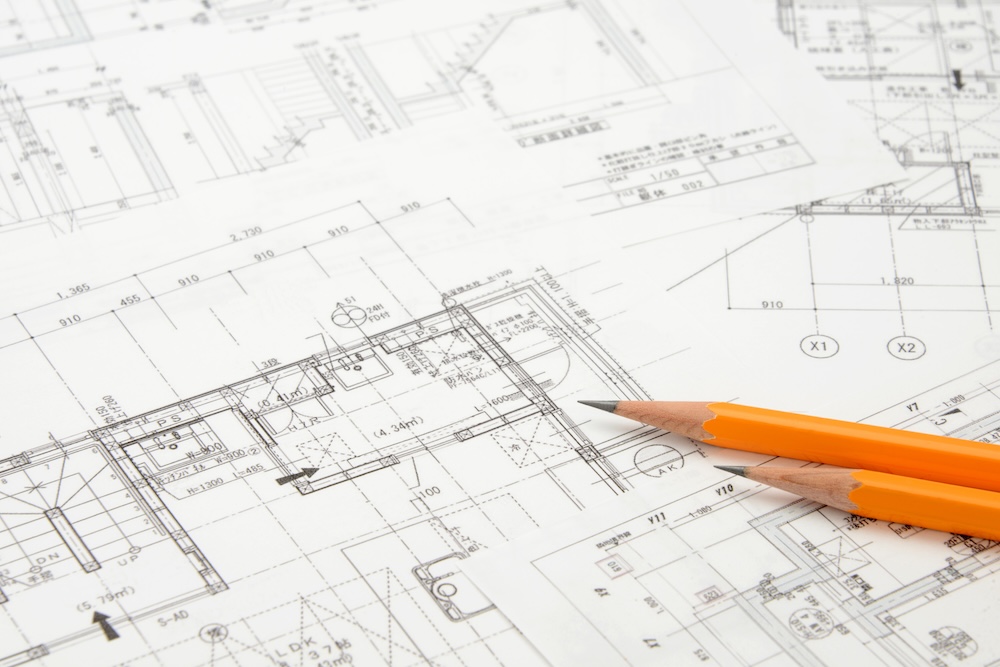
この章では、4号建築物の定義、それに関連する特例の内容、そしてその特例がどのように適用されているかについて深く掘り下げます。
さらに、法改正によってどのような変更が導入されたのかを詳しく説明し、これが建築確認申請の手順にどのように影響するかを説明します。
4号建築物とは、建築基準法において特に小規模な建築物と定められています。
該当する建物は、木造の場合、高さ13メートル以下で、屋根の高さが9メートル以下、かつ2階建てまでのものや、延べ床面積が500平方メートル以下の建物です。
また、木造以外では、単層で延べ床面積が200平方メートル以下の建物が含まれます。
こうした規模の建物について、特定の地域や状況下では、建築確認申請の手続きが簡略化されるため、迅速に工事を開始することが可能になります。
しかし、特例を適用するためには建築士が設計に関わる必要があり、その対象となる地域や条件が細かく規定されていることから、設計段階での正確な理解が必要です。
続いて、この「特例」について説明します。
4号特例とは、4号建築物に対して適用される建築確認申請の手続きを一部省略できる制度です。
この制度の大きな利点は、建築士によって設計された場合、通常必要とされる確認申請の書類の一部を省略できることにあります。これにより、申請から承認までの時間を短縮し、建築プロジェクトの進行をスムーズにすることができるからです。
特に、緊急を要する小規模プロジェクトやコスト削減が求められる場合に有効です。しかしながら、この特例は建築士が設計した建物に限られ、そうでない場合は通常の申請手続きを経なければなりません。
また、安全性を確保するために、「構造計算」を省略できるわけではなく、建築基準法に基づいた厳格な構造審査が行われます。
そのため、建築士としては設計時においても法的要件を十分に理解し、適切な設計を心がける必要があるといえるのです。
2025年に予定されている建築基準法の改正では、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」が導入されます。それぞれに異なる規格が設定されるため、従来の4号建築物に適用されていた緩和措置が見直されることになるのです。
特に重要なのは、すべての新築建物に対して「省エネ基準の適合」が義務付けられる点です。この変更は、省エネ性能の向上だけでなく、地球温暖化対策に寄与することも期待されています。
改正によって、建物のエネルギー効率が高められることは、運用コストの削減にも直結し、将来的には不動産市場においても省エネ建物の評価が高まると考えられます。
そうしたことから、今回予定されている改正は、建築業界における環境基準の新たな基準を設け、それに伴う技術革新も進むことが想定されます。
とりわけ、工務店の経営者やマネージャーは、こうした新しい基準に適応できる自社の環境づくりが必要となります。
そこで、次に従来からの変更点を詳しくみていきましょう。

2025年の法改正による4号特例の廃止と、新設される新2号建築物、新3号建築物について詳しくみていきます。特に、今回の変更が建築業界にどのような影響をもたらすか、また、構造計算の要件の変更についてみていきます。
2025年4月の法改正で4号特例が廃止されると、特に小規模建築物の建築に関わる企業や専門家に大きな影響が及ぶことが予想されます。
新規定の導入により、特定の建築物に対する確認申請の手続きが厳格化されるため、設計から施工、検査に至るまでの全工程で新たな対応が必要となります。
この変更の目的は、建物の安全性と環境適応性をさらに向上させることにありますが、同時に建築業者にはこれまで以上に詳細な準備と計画が大切になります。
具体的には、新たに設計基準や構造安全性の確認が強化されるため、これまでの設計アプローチを見直し、適合するための技術習得が急務となるでしょう。
これにより、建築設計の初期段階での時間とコストが増加する可能性があることから、工務店では、事前の対策と準備が重要になると考えられるのです。
新設される「新2号建築物」と「新3号建築物」は、それぞれ異なる規格と用途を持ちます。
新2号建築物は木造の場合、2階建てや延べ面積が200平方メートルを超える平屋建てが含まれます。一方、新3号建築物は延べ面積200平方メートル以下の木造平屋建てが対象です。
こうした区分によって、必要な建築確認の基準が変わり、それぞれの建物の安全性やエネルギー効率についての詳細な確認が必要になります。
このため、工務店や設計士は、新たな基準に対応するための綿密な計画と対策を練る必要があります。
特に、新2号建築物については、その構造安全性や省エネ基準の遵守が重要視されるため、設計から施工、検査に至るまでの各段階での厳格な管理が大切になるといえるでしょう。
現行の4号特例では、一部の小規模建築物において構造計算の提出が免除されることがありますが、2025年の法改正により、これらの免除規定が見直されます。
改正後は、全ての建築物に対してより厳格な構造安全基準が適用されることになり、自然災害に対する耐久性や安全性が強化されます。
これにより、工務店や設計士は新たに定められた構造計算基準に従って、より詳細な構造評価を行う必要が生じます。
この変更は、建物の安全を最優先に考える現代の建築環境において、避けて通れない要件となるでしょう。したがって、工務店では、改正内容を正確に理解し、適切な設計と構造評価を行うことがますます重要になるのです。
今回は4号建築物の確認申請についてお伝えしました。
以下に、本記事の内容を要約します。
この記事を通じて、4号建築物における確認申請の現行基準と、予定されている法改正についての理解を深めていただけたことと思います。
特に工務店では、構造計算等を通した設計から確認申請に至るまでのプロセスにおいて、最新の情報を常に把握し続けることが重要となります。
私たち「Make House」は、こうした構造計算についても、最新の基準に対応したサポートを行っております。「Make House」のサービスは、さまざまな課題を抱える地域の工務店様のお悩みを、豊富な実績と経験で解決いたします。
ぜひ、Make Houseにお問い合わせください!