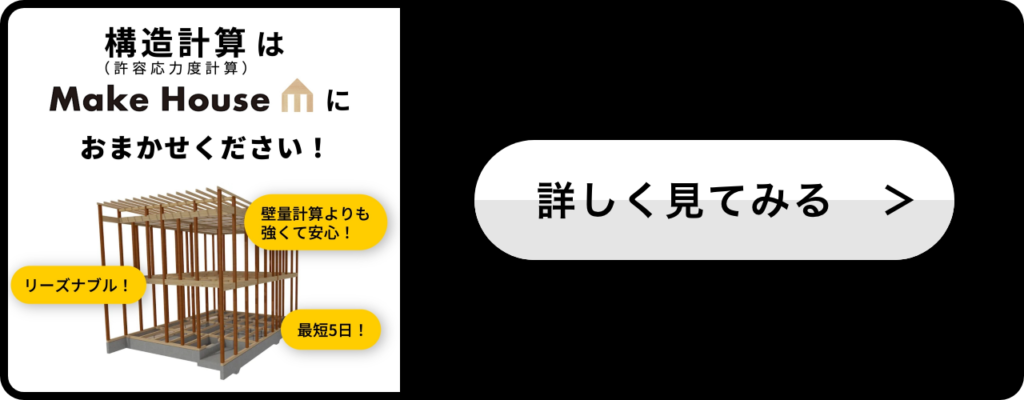「構造計算適合性判定」は、耐震偽装事件を発端として、平成27年に法制化された仕組みです。そのため、工務店における経営者やマネージャーは、建築物の安全や顧客からの信頼を得るため、このルールをしっかり守ることが欠かせない業務の1つとなります。
また、2025年4月より、建築基準法の改正で構造計算の適用範囲が拡大されます。こうしたことから、構造計算適合性判定について、法改正が施行される前の今だからこそ、もう一度確認する必要があるといえるのです。
そこでこの記事では、構造計算適合性判定の内容と重要性をわかりやすくお伝えします。読み進めることで、構造計算適合性判定の仕組みはもちろん、「構造計算」がより重要な位置づけになることもお分かりいただけます。
さっそく、構造計算適合性判定の概要からみていきましょう。
この記事のポイント

「構造計算適合性判定」とは、第3者機関が、建築物の構造計算について安全性を判断する仕組みのことです。
まず、構造計算は、建物が安全であるかを数字で示す1つの方法です。工務店が扱う建築物は、自然災害に強い構造を持たせることが必要となるため、計画段階で安全性に対する計算(=構造計算)を行うことが必要になります。
この構造計算に、外部からの判定を加えることで、建築物が法的な安全基準に適合しているかどうかをより適切に確認できるというわけです。
では、その具体的な基準を次の項でみていきます。
日本建築センター(一般社団法人)によれば、構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記のように定められています。
- 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物)
- 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
- 許容応力度等計算(ルート2)又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの
※上記1.2.について、許容応力度等計算(ルート2)審査対応機関に確認申請する場合、許容応力度等計算(ルート2)については、
構造計算適合性判定の対象外です。
※軽微な変更に該当する場合は、変更申請の必要はありません。なお、当該計画の変更が「軽微な変更(施行規則第3条の2第1項
各号)」に該当するかどうかについては、建築主事又は確認検査機関にご確認ください。
引用元:https://www.bcj.or.jp/judgment/outline/
つまり、ある一定の大きさを持つ建物については、その地域の都道府県知事や、指定された構造計算適合性判定ができる機関の「構造計算適合性判定」が必要とされているのです。
そういったことから、工務店は、上記に該当する建築物の構造計算適合性判定に向けた「外部機関とのやり取り」が発生します。そのため、工務店の経営層が、構造計算適合性判定の大まかな流れを掴むことが大切です。
次は、その構造計算適合性判定の流れについて深掘りしていきます。
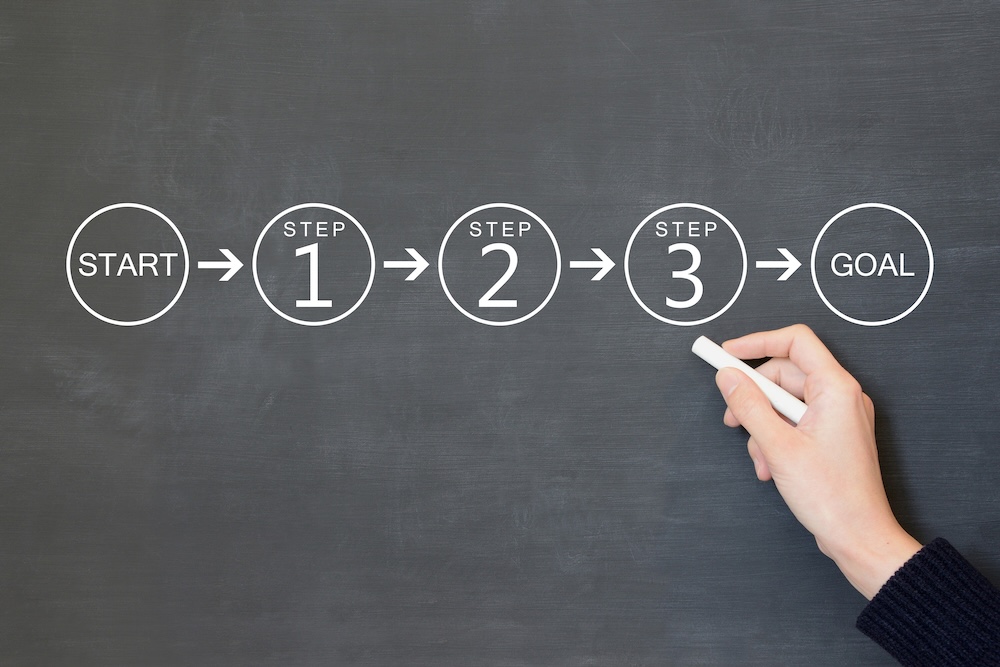
構造計算適合性判定について、大まかな流れを説明します。
構造計算適合性判定は、「事前申請」と「本申請」があります。
事前申請は、スムーズな本申請の通過を実現するために行われます。事前申請なしでも本申請を行うことは可能です。しかし、申請時に不備等がある場合、結果として申請業務に大きな時間がかかってしまう可能性もあります。
では次に、本申請の流れをみていきます。
本申請は、おおまかに以下の3つがあります。
①本申請
建築主(=工務店)が、必要な書類を用意し、機関に申請を行います。この段階で、建築物の構造や安全性に関する詳細な情報が審査機関に提出されます。
②審査
審査機関は、建築主から提出された資料を基に、建築物が建築基準法に沿っているかどうかをチェックします。もし問題があれば、修正(=補正、追加説明)を求められることがあります。
③適合判定の交付
すべての審査がクリアされると、建築物が基準に合っているという「適合通知書」が交付されます。
全体の審査期間は、2~7週間程度となります。ただし、何か問題があって書類の修正が必要な場合は、その修正期間は審査時間に含まれません。
以上が、構造計算適合性判定の流れになります。
ここまでお伝えした内容から分かることは、工務店の経営課題の1つともいえる「構造計算にかかわる業務」が、構造計算適合性判定の手順を含めることで、より大きな業務負担につながる可能性が高いことです。
そのため、地域で工務店を営む経営層やマネージャーは、構造計算適合性判定の土台となる構造計算に、従来よりも十分な時間をかけて取り組むことが必要となります。
そこで次は、工務店が、構造計算の課題をどう解決するかについて記します。
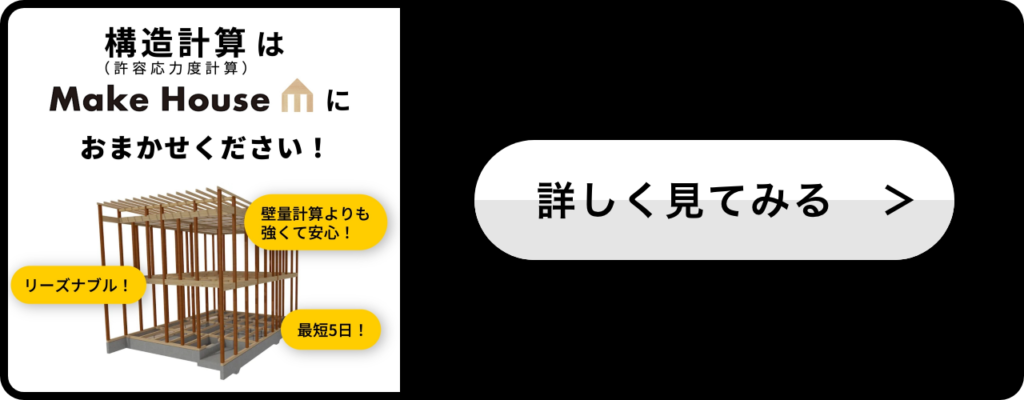
構造計算は、建築物が自然災害時にも崩壊しない強度を有しているかを数値で証明します。これにより、経営者が行う安全への対策は、法的な義務だけでなく、顧客の生命・財産を守る可能性をより高めることにもつながります。
一方、工務店が構造計算で直面する主な課題には、資材高騰によるコストの問題や、専門的な人材不足・若手を中心とする人手不足に起因するリソース制約があります。
特に中小規模の工務店では、こうした課題が事業の持続可能性に大きな影響を与えることがあるため、より効率的な業務プロセスを作ることが欠かせません。
具体的な解決策としては、最新の計算ソフトウェアの活用が挙げられます。これにより、手作業で行っていた計算を自動化し、時間を大幅に短縮することが可能になります。
また、ソフトウェアを使用することで、計算ミスを減少させ、より正確なデータに基づいた設計が行えるようになります。
さらに、外部の専門機関との協力を深めることで、専門知識が不足している問題を解消できます。これにより、工務店は構造計算の品質を保ちつつ、コストを抑えることができるため、全体の事業効率が向上すると考えられるのです。
今回は、構造計算適合性判定の概要から、工務店の課題と解決策について詳しくお伝えしました。
本記事の重要なポイントをおさらいします。
さて、構造計算適合性判定に関わる業務負担を減らすには、新しい技術の導入が必要となります。一方で、さまざまな経営課題を抱える地域の工務店にとって、有資格者の採用やソフト導入へのハードルは、決して低いものではないでしょう。
そこでおすすめするのが「外注化」です。
豊富な実績と確かな知識を持つ「他の機関」と連携することで、工務店の経営者やマネージャーが構造計算の知識を深めながら、新しい技術を活用することができます。
私たち「Make House」は、地域の工務店様に対し、構造計算を含めたさまざまな業務を支援させていただきます。
お困りの際は、ぜひ「Make Kouse」にご相談ください!