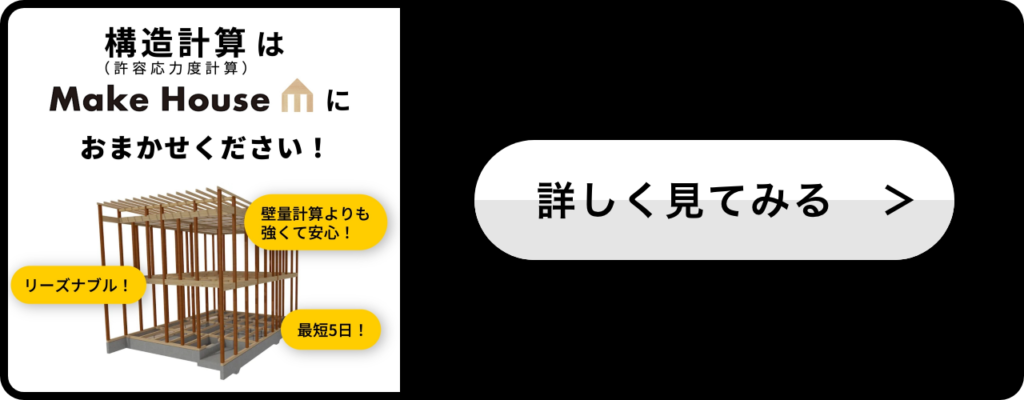木造住宅の建築に携わる工務店経営者の皆さんは、構造計算の必要性や法改正に関する情報に注目していることでしょう。特に、2025年の建築基準法の改正は、木造住宅の構造計算に大きな影響を与えます。
この改正により、従来は簡易的な壁量計算が許されていた多くの木造住宅において、構造計算の必要性が高まる可能性があります。
そこで今回は、構造計算および法改正の変更点と、それが工務店経営にどのように影響を与えるかを解説し、今後の対策について考えます。
さっそく、詳しい内容についてみていきましょう。
目次

木造住宅の構造計算とは、建物が安全に機能するために必要な計算のことです。建物にかかる重さ、風圧、地震力などの外力に対して、構造体がどのように反応するかを計算し、安全性を確認する作業が含まれます。
多くの木造住宅では、簡易的な壁量計算によって構造安全性が確認されてきました。しかし、これからは構造計算を行うことで、より高い安全性を持たせることが求められるようになります。
構造計算は、専門的で時間がかかる作業とされ、2階建ての小規模な木造住宅においては省略されることが多かったのです。しかし、2025年の建築基準法の改正により、この状況は大きく変わる見込みです。

構造計算は、木造住宅の安全性を確保するために行われるプロセスの1つです。
この計算では、建物が受けるさまざまな負荷や力に対して、構造が安全に耐えることができるかを科学的に検証します。
たとえば、建物の自重や積載荷重、地震や風圧などの外力に対する構造部材の応力(抵抗力)や変形を計算します。これにより、建物が安全基準を満たしているか、またどの程度の安全マージンがあるかを把握することができます。
構造計算には、許容応力度計算や壁量計算など、さまざまな方法があります。
許容応力度計算では、部材ごとに応力度が許容範囲内に収まっているかを確かめます。壁量計算は、特に2階建て以下の一定規模未満の木造住宅において適用される比較的簡易な計算方法です。
これらの計算は、建築物の安全性を検証し、住宅の品質を保証する上で欠かせないものです。
木造住宅の構造計算には、主に4つの計算方法が存在します。これらの方法は、建物の安全性と耐久性を確保するために重要な役割を果たします。
許容応力度計算は、建物の自重と地震や台風時にかかる応力が、使用される材料の耐力を超えないことを確認します。
自重とは、建物そのものの重さであり、地震や台風時の応力は、それらの状況下で建物にかかる力を指します。
この計算では、建物が日常的な状況と自然災害時においても安全に機能することを確認することが目的です。
ルート1の計算に加えて、建物の変形やバランスが特定の数値以下であることを確認します。
これにより、建物が過度に歪んだり、不均衡になったりすることなく、構造的に安定していることを保証します。
ルート2までの計算を行った建物は、一般的に構造計算された建物と呼ばれます。
この計算方法は、大地震が発生した場合に建物が部分的に損傷しても全壊に至らないことを確認することを目的としています。
これは、特に地震活動が活発な地域において重要な計算であり、建物が大規模な災害に対して一定の耐久性を持つことを保証します。
建物の耐震性能をより詳細に分析するための高度な計算方法です。
限界耐力計算では、建物が耐えうる最大の力を計算し、時刻暦応答解析では、地震発生時の建物の応答を時間の経過に応じて詳細に分析します。
これにより、建物が最悪のシナリオにおいても安全性を保持することを確認することができます。
こうした計算方法は、木造住宅の設計と建築において、その安全性と信頼性を確保するために欠かせません。
さて、ここまでは構造計算とその具体的な手法について網羅的に説明してきました。2025年4月より施行される建築基準法改正では、特例として簡易的な計算で良いとされてきた木造住宅にも、許容応力度計算の適用範囲が拡大されます。次は、この点について詳しくお伝えしていきます。
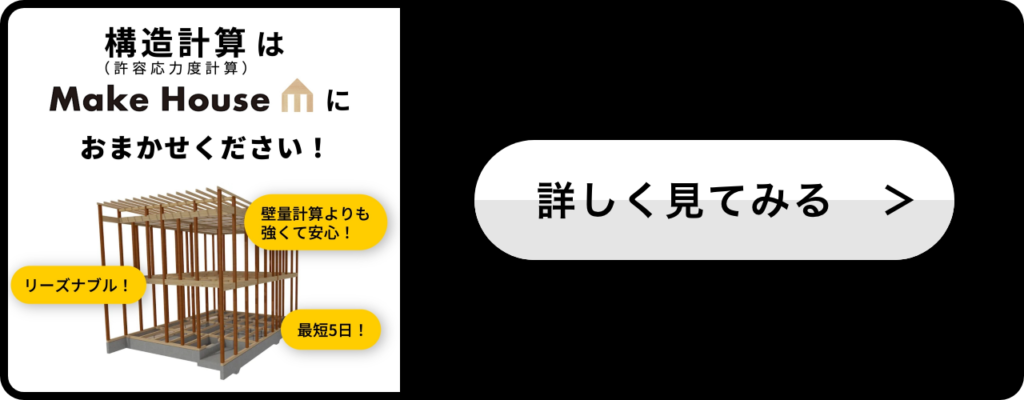

2025年の法改正では、特に木造住宅の建築基準に大きな変更が予定されています。現在の建築基準法では、以下の条件を満たす木造住宅は「4号建築物」として分類され、構造計算書の提出が不要とされています。
この「4号特例」により、多くの木造住宅が簡易的な壁量計算による安全性の確認で済まされてきました。しかし、2025年の法改正によって、これまで建築確認・検査の対象ではなかった、4号特例に該当する建築物の範囲が縮小されます。
具体的な数字で言うと、平屋または200㎡以下の建物のみが、今後構造計算書の提出免除の対象となり、それ以外の木造建築物では構造計算書の提出が必要になります。
これにより、国内の木造住宅の多くは新しい基準に適合するための構造計算を必要とすることになります。
次は、2025年の法改正が具体的に工務店にどのような影響を与えるのかを掘り下げていきます。
改正法では、構造計算が義務化される範囲が拡大されるため、多くの木造住宅で構造計算が必要になると予想されます。これにより、工務店は構造計算の知識を持つ専門家と連携するか、あるいは自社で構造計算のスキルを身につける必要が出てきます。
また、構造計算を行うことで、耐震性などの安全性が高まるだけでなく、設計の自由度も向上します。これは、工務店が顧客に対してより魅力的な提案をする機会にもなるでしょう。
その一方で、設計や建築にかかるコストや時間が増加する可能性も考慮する必要があります。工務店や設計事務所にとっては、これまでの設計プロセスの見直しや、構造計算の知識を習得する必要が生じるため、大きな影響をもたらすでしょう。
今回お伝えしたように、木造住宅の構造計算に関わる法改正は、工務店に大きな影響をもたらします。工務店経営者の皆さまは、決して簡単ではない資格保持者の雇用や、信頼できる相談先の選定にお悩みではないでしょうか。
Make Houseでは、構造計算を含む住宅設計の全面的なサポートサービスをご提供しています。工務店様が直面する構造計算の複雑さを軽減するのはもちろんのこと、業務効率化を実現するためのご相談も承っております。
2025年の法改正に対応するためには、工務店様も新たな知識と技術の習得が必要です。Make Houseでは、そうした工務店様のニーズに応え、一括での構造計算対応サービスも提供しています。さらに、法改正によって求められる高い安全基準を満たしながら、設計プロセスの効率化を実現するために、二次元CADから三次元CADへの移行など、最新の技術も活用しています。
弊社のサービスをご活用いただくことにより、工務店様は安心して品質の高い住宅建築に専念いただけるようになります。法改正の前であっても、これからの取り組みに関してご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。